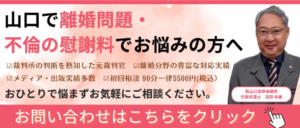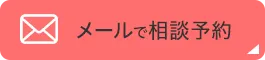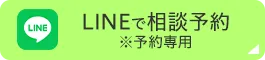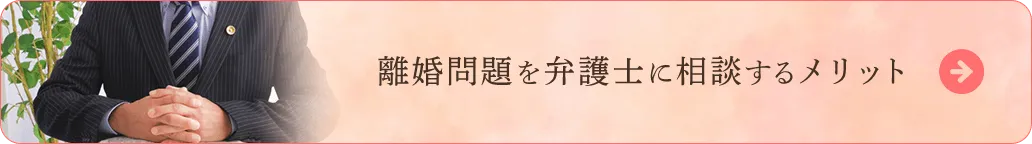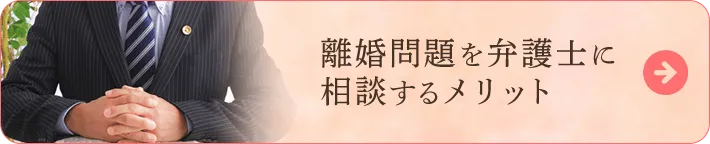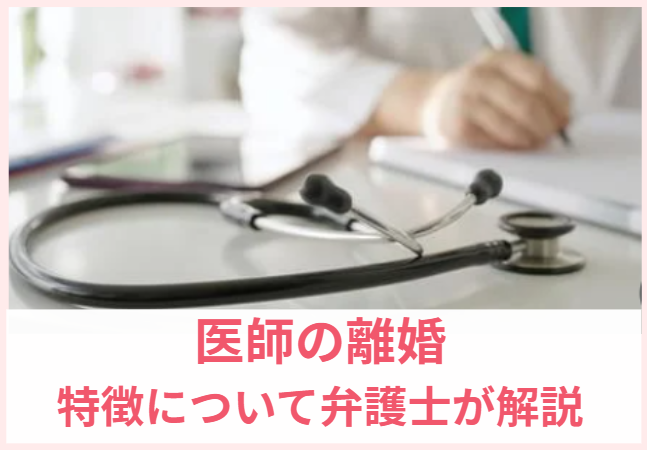
1.医師の離婚の特徴
医師(歯科医師を含みます。)との離婚の特徴があるとすれば、高収入・高資産のイメージがつきまとうことです。現実に、高収入を謳歌している医師を相手の離婚もあれば、実際には、経営苦に陥っている医師を相手に離婚する場合もあります。ただし、開業医の場合には、表面的には経営主体は医療法人であることが多いため、法人は経営苦であっても、医師個人の収入は経費となる給与・賞与として高額を払い出していることもあります。
離婚したいと思う配偶者も医師の場合もあれば、医師資格は持たない医療従事者であったり、専業主婦の場合もあります。
子弟を医師にしたいという欲求から、夫婦間の子どもが医学部進学を目指していたり、医学部在学中であったりすることも特徴としてあげられます。
2.医師の財産分与
① 開業医の場合
医師を相手に離婚したいと思うとき、相手が経営するクリニックの財産価値の半分が欲しいと思うのは人情かもしれませんが、なかなか、そうもいきません。
まず、開業医がクリニックを経営する場合、多くは医療法人を設立して、医療法人の経営下で、経営者の医師は医療法人から給与をもらう形を取ることが多いです。
医療法人は、かつては会社のように、出資した者が持分という権利を持つ、持分型の医療法人が主流でした。このような持分型医療法人の場合には、持分権者である相手方医師の有する持分額が分与対象財産を構成するわけです。
しかし、医療法の改正により、2007年4月以降設立の医療法人は経営者の私物化を回避して公益性を重視することとなったため、持分なし医療法人となりました。したがいまして、2007年4月以降に開業した開業医が相手の離婚では、医療法人の価値は分与対象財産としてカウントされることはなくなりました。
そうすると、現時点では、2007年3月以前に設立された医療法人の持分を相手の医師が有する場合には、その持分の財産価値・評価額は分与対象財産としてカウントされることがあるというだけにとどまることになります。
また、医師が相手の財産分与の場合、離婚希望者側も医師であり、医療法人の経営に寄与してきたという場合であったり、相手が医師免許取得以前から婚姻し、苦学生時代を経済的に支えて、医師免許取得に尽力したという事情でもない限り、分与率は2分の1ではありません。医師が高資産を形成できたのは、内助の功によるわけではなく、医師免許のおかげです。そのため、医師免許取得後に婚姻した配偶者であるというだけの場合には、分与率は、7対3あたりと判断される傾向にあります。
② 勤務医の場合
相手が勤務医である場合には、通常の会社員と離婚する場合と同様です。夫婦双方の資産・負債を合算して、プラス部分が出れば、そのプラス部分を双方が2分の1ずつ取得するように調整していきます。
分与率も、勤務医の場合には、開業医ほど高収入ではないことも多いため、2分の1で解決する事例も見受けられます。
3.医師の離婚における婚姻費用や養育費の注意点
医師の離婚の場合でも、婚姻費用や養育費の算定の仕方自体は、ふつうの会社員や自営業者との離婚の場合と同様です。
何が違うかといえば、医師の配偶者には、高い消費習慣が身に付いてしまっているという点です。婚姻費用や養育費の調停などでは、最高裁の公表する養育費等の算定表をベースに取り決めることがおおいわけですが、医師の収入はこの算定表の範囲内に収まらないことがよくあります。そのため、算定表のもとになっている養育費・婚姻費用の算定式に従って試算することになるのですが、単純に試算すると、かなりの高額となってしまうことがあります。
権利者は、高額であれば満足ですが、落とし穴がある点に注意が必要です。
開業医の場合、医療法人が経営苦であっても、医師個人への給与の支給自体は経費として支出できますので、給与自体は高額となっていることがありますが、当人が経営している医療法人の財政状態は青色吐息であり、金融機関からの借金で自転車操業をしているケースも見受けられます。このようなケースで、養育費・婚姻費用の試算結果どおりに、養育費・婚姻費用を取り決めてみても、支払主体である医療法人がつぶれてしまえば、養育費や婚姻費用は止まってしまうことになります。
医師の配偶者は高額な消費態度が身に付いてしまっていることが多いため、そのような点に無頓着なことがありますが、経営内容にそぐわない、あまりに高額な婚姻費用・養育費の取り決めはいずれ自分の首を絞めることになりますので要注意です。
また、子弟が医学部進学を目指していたり、医学部在学中であったり、ということも多いため、養育費の終期も6年生の医学部修了に合わせて取り決めがちです。医学部生は実験や実習等も多く、アルバイトをしている暇がないということも手伝って、そのような取り決めがされるケースが多く見られがちです。
この点も、開業医が相手の離婚の場合には、医療法人の経営状態とにらみ合わせて無理のない設定にしておかないと、我が子につけが回ることになってしまいます。
総じて、表面上の数字では豪華な養育費が決まりがちな医師との離婚ですが、実態に応じて、確実な支払いが期待できる限度にとどめておくことも重要です。
4.妻を雇用している場合の対応
離婚しようとしている医師が個人として、あるいは医療法人の経営者として、妻を事務員等で雇用しているというケースもまま見受けられます。
単なる専従者として税務申告の際に節税だけで活用しているような場合には、就労の実態がないことも多いですから、その場合には、専従者給与の計上をやめればよいだけの話ですが、そうではなくて、就労実態があり、社会保険等にも労働者として加入させているような場合には、話は別です。
離婚問題だけで解決というわけにはいかず、労働者として円満退職に導くことができなければ、個別労使紛争として立派に労働審判等の対象となってしまう危険すらあります。就労実態がある場合に、退職方向で解決したい場合には、他の従業員の方と同じく、就業規則に従って、退職金を支給したり、合意退職に持ち込んだりする努力が必要となります。不当解雇をしてしまうと、解雇が無効という前提で解決時までの未払賃金等の支払いを余儀なくさせられるケースもありますので、くれぐれも注意してください。
5.まずはご相談ください。
医師の離婚には、いくつか注意点があります。妻を雇用していて就労実態があるときには、離婚問題とは別に労働問題もからんできます。離婚も個別労使紛争も弁護士に相談して動いた方がよいと思われる分野です。当事務所は、個別労使紛争の解決にも努力している事務所です。まずは、ご相談ください。