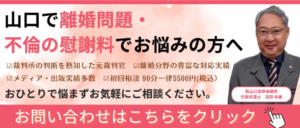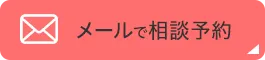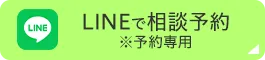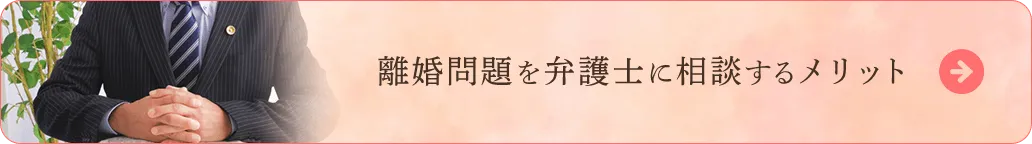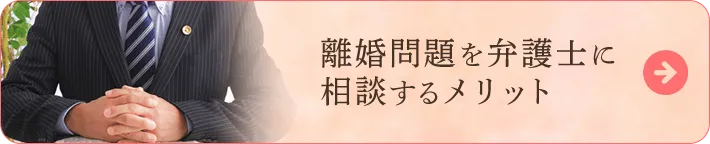1.何が問題なの?ADHDの人との夫婦生活
配偶者がADHDである場合には、その特性に合わせた日常生活の対応や配偶者の特性を認識し、理解した上で、受け入れられれば、問題なく夫婦生活が送れると思います。他方で、配偶者自身がADHDであると自覚認識していないケースも少なくありません。そうなると、あなたも配偶者の言動の真意が図りかねたり、どのように対処していいのか、困ってしまうことも出てくると思います。
ADHDは、注意欠如・多動症とも言われ、発達障害の一種であり、「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性が持続的に現れる状態を指します。集中力が続かない特性の表れとして、①忘れ物が多かったり、②順序立てて行動するのが苦手であったり、③約束や期限を忘れることがあったりします。また、「多動・衝動性」の現れとして、①じっとしていられない、②おしゃべりが止まらない、③順番を待つのが苦手、④思いついたことをすぐ行動に移してしまう、といったような言動が見られがちです。
ADHDをはじめとする発達障害の方は、脳の特性が多数派の人たちと異なるとされています。別段、病気でも異常でもないといわれていますが、やはり多数派の人たちの脳の特性からすれば、行動パターンとしては目立ったものとなってしまいます。そのため、幼少期に発見されれば、社会適応訓練を積んで、多数派の人たちの行動パターンと調和するように行動できるようにもなると言われています。
他方で、ADHDをはじめとする発達障害の方と対峙する側も、発達障害の脳の特性を理解できないまでも、知識として知っておくだけで、一見、逸脱行動に見えるような言動であっても、悪気のない行動であると言い聞かせて、それなりに対処することは可能です。
ただし、ADHDを持っている側が自分のことを正しく認識していない場合であって、なおかつ、配偶者側も発達障害に関する知識すら有していない場合には、約束や期限を守らず、おしゃべりが止まらない割に、自分の興味のある事柄については過集中となり、妻として家事育児を放ったらかしにしたり、夫として仕事に頻繁に遅刻欠勤が目立ったりという状態を前にした配偶者には、ぐうたら妻に見えたり、無能な夫に見えたりということがあり、次第に愛情も冷めてきてしまうこともあります。発達障害は脳の特性ですから、注意して今後はこのようなことはやめて!といくら叫んでも、直ることはないのです。
2.「ADHDであること」だけを理由とした離婚は難しい
裁判上の離婚原因を定める民法770条1項4号には、配偶者が重大な精神病にかかり、回復不能な場合には、離婚合意ができなくても、裁判で離婚することができると定められています。
多数派の脳を持つ人々からみれば、発達障害の勉強をしていないと、ADHDをはじめとする発達障害の脳を持つ人の行動特性は対処困難なものであり、時として、疲弊してしまい、夫婦関係を維持することは難しく感じてしまうことはあろうかと思います。しかし、ADHDをはじめとする発達障害は、脳の特性に過ぎず、精神病でも、異常でもありません。ADHDをはじめとする発達障害であることだけを理由とした離婚請求は難しいと思われます。
3.ADHDのパートナーと離婚が認められるケース
それでは、ADHDのパートナーと離婚が認められるケースはどういう場合があるのでしょうか。
結論としては、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められる場合には、ADHDパートナーとの離婚が可能となってくると言えるでしょう。といっても、これだけでは抽象的ですので、具体的には、次のようなケースならば、離婚可能であろうと考えられます。
① 相手が離婚に合意している(協議・調停離婚)
ADHDを持つ側も、自分の特性を理解した上で対応してくれるパートナーでなければ、一緒に生活するのは苦痛だと感じることが少なくありません。そのような場合には、どちらが悪かったかという認識は正反対であるにしても、双方が離婚したいという気持を持つ場合があります。離婚条件で対立する要素がなければ、協議離婚することも可能ですし、離婚条件の調整で家裁の調停を使っても、離婚条件の調整もできれば、調停離婚することは可能です。
② ADHDと同時に「DV・モラハラ」がある
ADHDをはじめとする発達障害のバリエイションは様々ですが、発達障害自体は脳の特性に過ぎません。それが少数派であるというだけです。ただ、そうした脳の特性とは別に、「人格障害」を併有する場合があります。とりわけ、「自己愛性人格障害」を併有する配偶者であると、現象としては、一方的にあなたを誹謗中傷し、責め立てるモラハラ行動に出たり、社会的隔離・執拗な暴言・限度を超える脅迫・身体的暴力というような、いわゆるDVに出たりすることがあります。
ここにADHDの特性が加わり、モラハラ言動やDVに過集中の態度が加わると、その加害配偶者との信頼関係を維持することは不可能となります。もちろん、関係の再構築は、強い恐怖に阻まれて無理となります。こうなると、婚姻関係が破綻したものとして、民法770条1項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものと認められる場合が多くなるといえます。
③ そのほかに「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとき
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」は、極端な言い方をすれば、たとえ「性格の不一致」のように本人に責任のないことに端を発していても、さまざまな事情の積み重ねによって、夫婦関係が悪化してしまい、回復不能となれば、離婚を認める離婚原因です。
ADHD自体は本人に責任のない、脳の特性に過ぎませんが、しかし、それでも、注意力散漫に起因して、重大な交通事故を起こして、家庭を経済的にも心理的にも不安に陥れ、次第に夫婦仲が冷え込んでいったり、あるいは、自分が夢中になっていることに熱中して、毎日のように、配偶者や子どもの食事の支度がおろそかになったり、ほかの家事や学校対応も不備になったりしていき、次第に夫婦仲が冷え込んでいくようなケースでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認定される場合も出てくると考えられます。
④ 相手が働かない、生活費を払ってくれない
ADHD自体は非難すべきものではありませんが、衝動的な行動特性や、じっとしていられない行動特性などから、訓練を受けていないADHDの方の中には、職場の人間関係が不調となったりして、欠勤がちとなつたり、そもそも、夢中になっていることに熱中して出勤自体しなかったり、ということで、収入が減少するなどして、家族に生活費を入れることができなくなる場合もあり得ます。
このような場合は、状況によりけりですが、民法770条1項2号の「悪意の遺棄」、もしくは「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認定されて、離婚ができる場合があります。
4.ADHDを理由に「慰謝料」は請求できる?
基本的には難しいと思われます。慰謝料請求が認められるためには、加害者に不法行為が認定される必要があります。不法行為とは、故意または過失をもって、違法行為により、他人に損害を与える加害行為のことをさしますが、離婚になりそうな夫婦関係の一方がADHDをはじめとする発達障害であることを、自分自身、知らない場合が多く、ADHDの特性に起因する各種言動自体を注意しなければならないという自覚すらありません。何も知識がなければ、ADHDをはじめとする発達障害の特性に直面すると、困惑することが多いものですが、それはたいていの場合、ADHDをはじめとする発達障害の人々が、その場の空気を読めず、違和感のある行動を取りがちであるためであると思われます。そこには、加害者に故意があるわけでもなければ、過失があるわけでもありません。違和感のある行動で、直面させられた側としては対処に困るとはいえ、そこに違法行為があるわけでもありません。一般に、単なる「性格の不一致」による婚姻破綻だけでは、慰謝料の請求は難しいと言われますが、それと同様に、脳の一特性に過ぎないADHDを理由とする慰謝料請求は困難であると考えられます。
もっとも、子ども時代に既に発達障害の検査・診断を受けており、自らが発達障害であることを分かっていて、社会適応の訓練も受けていたにもかかわらず、そのことを秘匿して、結婚し、結婚生活では過去の治療・訓練の成果を意図的に無視して配偶者に衝動行動などで迷惑をかけ続けて、婚姻関係を破綻させたというような場合には、慰謝料請求は可能であろうと考えられます。とはいえ、的確な証拠を集めて、立証することは難しそうです。
5.ADHDがあると財産分与に何か影響がある?
ADHDと慰謝料請求については、このように考えなければならないことがありますが、財産分与については、相手にADHDがあるからといって、何かそれが影響して、特別な結論になるということはありません。
ただし、ADHDの相手の中には、過集中の行動特性の表れとして、自分名義の財産管理を徹底的に厳格に行っている方も見受けます。他方配偶者からすれば、そこまでしなくてもいいのにと思うような資産管理をしていることがあります。僅少額の資産であっても、株式投資等をして証券会社を利用している上に、証券会社も複数に分散させて、管理していたり、金融機関も地元の金融機関ではなく、ネットバンクや全く遠隔地の地方銀行の口座で預金管理をするなどというようにです。
財産分与の一番の課題は、請求相手の配偶者の財産状況の把握です。これがある程度できないと、財産分与請求を実現することは困難となります。
とりわけ、過集中の傾向があるADHD配偶者の中でも、銀行預金、株式・公社債等の資産管理を「趣味」としている方が相手の場合には、分与対象財産の把握に苦労させられることが多いです。
6.一人で我慢せずに弁護士にご相談ください。
ADHDの配偶者との離婚相談については、大多数のケースと違う配慮をする必要がある部分はありますが、打開できないケースばかりでもありません。何ができるか、どこまでできるか、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。